
葬儀において「心付け」という言葉を耳にしたことはありますか?
心付けとは、葬儀に関わる方々へ感謝の気持ちを込めて渡す金銭のことを指します。
しかし、誰に、どのように、いくら包むべきか迷うことも多いのではないでしょうか。
特に初めての葬儀であればなおさらです。
この記事では、心付けの必要性や相場、具体的な渡し方、さらには封筒の書き方やお札の入れ方まで、初心者向けに葬儀の心付けについてわかりやすく解説します。

心付けとは、葬儀を進行する際にお世話になる方々に感謝の気持ちを込めて渡す金銭や品物のことです。
これは、葬儀の進行をスムーズにするために欠かせない役割を果たす多くの人々に対するお礼の一環です。
例えば、葬儀では故人の搬送、納棺、通夜、葬儀告別式、火葬といった一連の流れを支えるために、葬儀業者、運転手、配膳スタッフ、火葬場のスタッフなど、数多くの専門家が関わります。
これらの方々の協力がなければ、葬儀を円滑に進行することは難しいでしょう。
心付けは、こうした支えとなってくれる方々に対して、遺族が感謝の意を表すための方法です。欧米の「チップ」と似た意味合いを持ちますが、日本では「お礼」の意味合いがより強調されます。
そのため、心付けは必ずしも義務ではなく、渡すかどうかは遺族の判断に委ねられます。
また、心付けの渡し方や金額は地域や個々の状況により異なるため、事前に確認することが重要です。
例えば、ある地域では心付けが不要とされることもありますし、葬儀社によっては心付けを受け取らない方針を持つところもあります。
そのため、葬儀の準備を進める際には、心付けについてのマナーや慣習を把握しておくことが大切です。
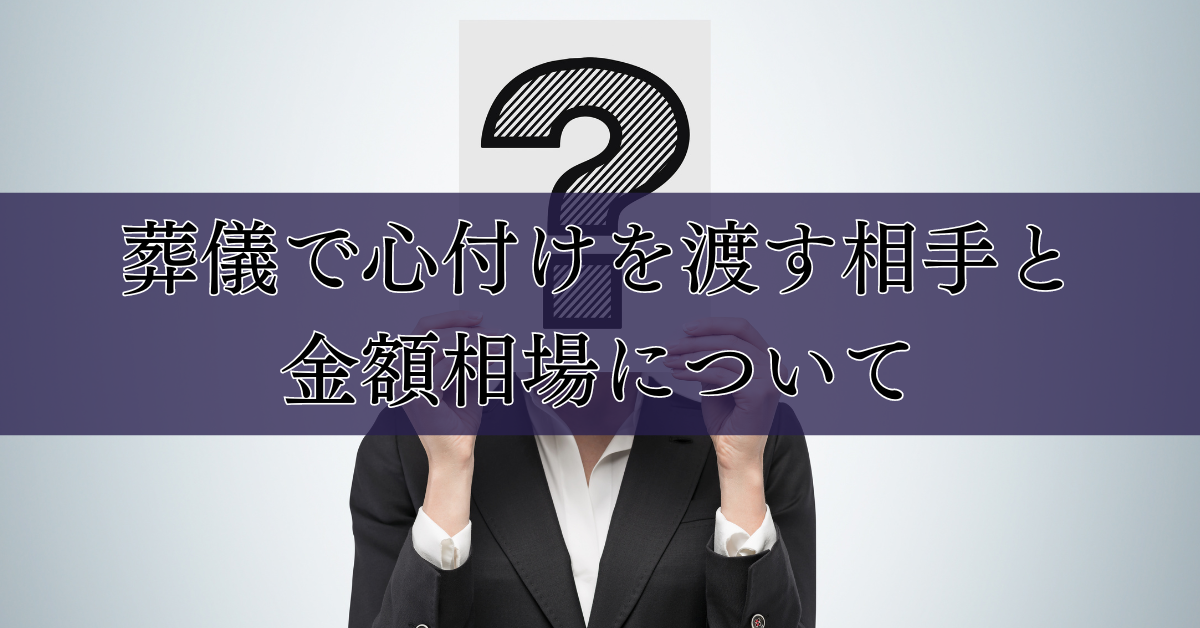
葬儀で心付けを渡す相手とその金額相場について、具体的に解説します。
心付けを渡すことで、葬儀の進行を支えてくれる方々に感謝の気持ちを伝えることができます。
以下では、主な相手とその相場を説明します。
葬儀社の担当者は、葬儀全体の進行を滞りなく行うために尽力してくれます。
担当者に心付けを渡す場合、一般的には5千円から1万円が目安です。
ただし、最近では心付けの受け取りを禁止している葬儀社も増えています。
心付けを渡す前に、葬儀社のルールを確認しておくことが大切です。
運転手への心付けと金額相場
葬儀では故人のご遺体や遺族の移動に車を利用します。運転手に対する心付けの相場は以下の通りです。
寝台車の運転手:
故人のご遺体を搬送する寝台車の運転手には、3千円から5千円が相場です。
寝台車が安置場所や葬儀場に到着した際に渡しましょう。
霊柩車の運転手:
故人のご遺体を葬儀会場から火葬場へ運ぶ霊柩車の運転手には、3千円から5千円が目安です。
霊柩車が葬儀会場に到着したときに渡します。
ハイヤーの運転手:
遺族や参列者の移動にハイヤーを利用する場合、心付けの相場は1千円程度です。
ハイヤーの手配料に心付けが含まれている場合もあるので、事前に確認しましょう。
マイクロバスの運転手:
多くの参列者を移動させるためのマイクロバスの運転手には、2千円から3千円が相場です。
火葬後、遺族と参列者が戻る際に渡します。
火葬場のスタッフに心付けを渡す場合の相場は以下の通りです。
ただし、公営の火葬場では心付けの受け取りを禁止している場合が多いので、事前に確認しましょう。
火葬炉係員:
火葬を取り仕切る火葬炉係員には、1人あたり3千円から5千円が一般的です。
火葬場に到着してから渡します。
休憩室係員:
参列者を休憩室に案内し、茶菓子を振る舞う休憩室係員には、1人あたり2千円から3千円が相場です。
火葬が終わる前に渡しましょう。
葬儀では、親戚や友人、近所の方々に手伝ってもらうことが多くあります。
以下はその相場です。
葬儀の案内、受付、台所係など:
これらの役割を担ってくれた方には、2千円から3千円が相場です。
葬儀終了後に渡しましょう。
世話役:
葬儀の進行や案内を担当する世話役には、代表世話役に1万円から3万円、その他の世話役には5千円から1万円が目安です。
心付けは葬儀当日または後日渡します。
心付けを準備する際は、相手に対する感謝の気持ちをしっかりと伝えることが重要です。
地域や葬儀社のルールに従い、適切なタイミングで心付けを渡しましょう。
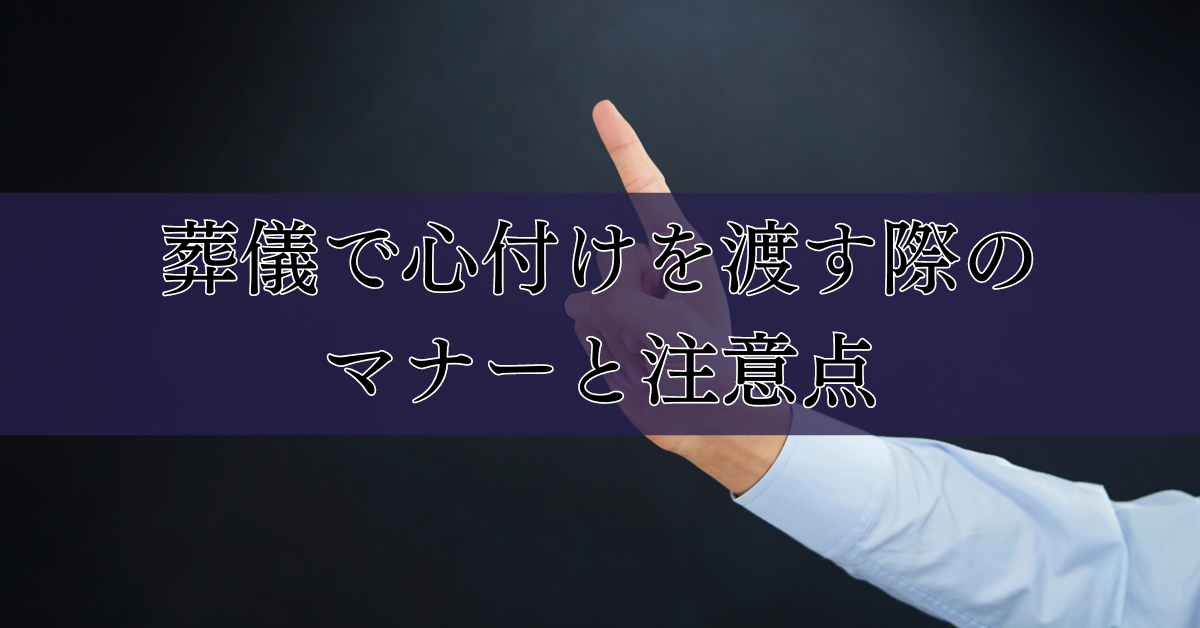
葬儀で心付けを渡す際には、正しいマナーを守ることで感謝の気持ちをより一層伝えることができます。
以下では、心付けを渡す際の具体的なマナーと注意点について解説します。
封筒や書き方
心付けをそのまま手渡しするのは避け、必ず封筒やぽち袋に入れて渡しましょう。
以下のポイントを押さえてください。
●封筒の選び方
白無地の封筒やぽち袋を使用します。金額が5千円以上の場合は、お札を折らずに入れられる封筒が適しています。
封筒の形式:
二重封筒は「不幸が重なる」と捉えられるため、一重封筒を使います。ぽち袋を使う場合、お札は三つ折りにして入れます。
表書き:
封筒の表には「志」「御礼」「心付け」と書きます。表書きの下か裏面に自分の氏名を記入します。この際、薄墨である必要はありません。
●心付けのお札について
心付けに使用するお札は、必ずしも新札である必要はありませんが、古く汚れたお札は避けましょう。
きれいな状態のお札を使用することが礼儀です。
●個々に直接手渡しする
心付けは、感謝の言葉と共に個々に直接手渡しするのが基本です。
直接渡せない場合は、信頼できる身内や葬儀社の担当者に依頼しても良いでしょう。
●葬儀費用に含まれていないか確認する
葬儀会社によっては、見積もりに心付けの費用が含まれている場合があります。
心付けを準備する前に、葬儀会社に確認して行き違いを防ぎましょう。
また、心付けの受け取りを禁止している葬儀会社も増えていますので、無理に渡すのは避けましょう。
●地域の慣習に合わせる
心付けには地域ごとに異なる慣習があります。
地域の事情に詳しい方や葬儀社の担当者に相談し、その地域の習慣に合わせて心付けを用意することが大切です。
最近では、心付けを不要とする葬儀社も増えています。
心付けを渡すことで相手に気を遣わせてしまう可能性もあるため、葬儀社の方針や地域の慣習を考慮して、適切に判断することが求められます。
心付けが不要な場合や受け取りを辞退された場合は、無理に渡す必要はありません。
心付けは、葬儀を円滑に進行してくれる方々への感謝の気持ちを伝える重要な手段です。
正しいマナーを守り、感謝の心を込めて丁寧に渡しましょう。
お電話での無料資料請求・ご相談は
お電話での無料資料請求・ご相談は
さがみ典礼の葬儀場を探す
さがみ典礼の葬儀プラン
さがみ典礼のお客様の声
コラム
さがみ典礼のご紹介