
訃報は突然やってくるものです。
しかし、仕事や家庭の事情、地理的な制約など、どうしても葬式に参列できないこともあるでしょう。
そのような状況で「葬式に行かないのは非常識ではないか」と心配する方も少なくありません。
本記事では、葬式に行けない場合のマナーや適切な対応方法について解説します。
参列できない場合でも、ご遺族への誠意をしっかりと伝えるための手段を知り、常識的で丁寧な対応を心がけることで、適切な弔意を示しましょう。
お電話での無料資料請求・ご相談は

葬式は故人を悼み、ご遺族に弔意を示すための重要な場ですが、やむを得ない事情で参列できない場合もあります。
では、葬式に行かないことは非常識なのでしょうか?結論から言えば、状況によっては参列しないことが必ずしも非常識と見なされるわけではありません。
葬式は突然発生するため、仕事の都合や体調不良などで参列が難しい場合もあるでしょう。
こうした理由を誠実に伝えることが重要です。
「やむを得ない事情」や「体調不良」など、柔らかい表現を用いて理由を説明し、早めにご遺族へ連絡することで非常識との見なされ方を防ぐことができます。
最近は家族のみで行う家族葬も増えており、その場合は一般参列が控えられるのが一般的です。
無理に参列しようとすることがかえってマナー違反とされることもあるため、案内の内容を尊重することが大切です。
葬式は故人と直接お別れをできる最後の場です。
「参列しなければ良かった」と後悔する可能性がある場合には、その選択を再考する価値があります。
自分自身の気持ちを整理し、参列するかどうかを判断しましょう。
葬式に行かないことは、事情次第で理解される場合もありますが、伝え方や対応次第で周囲からの印象は変わるものです。
適切なマナーを守り、心ある対応を心がけましょう。
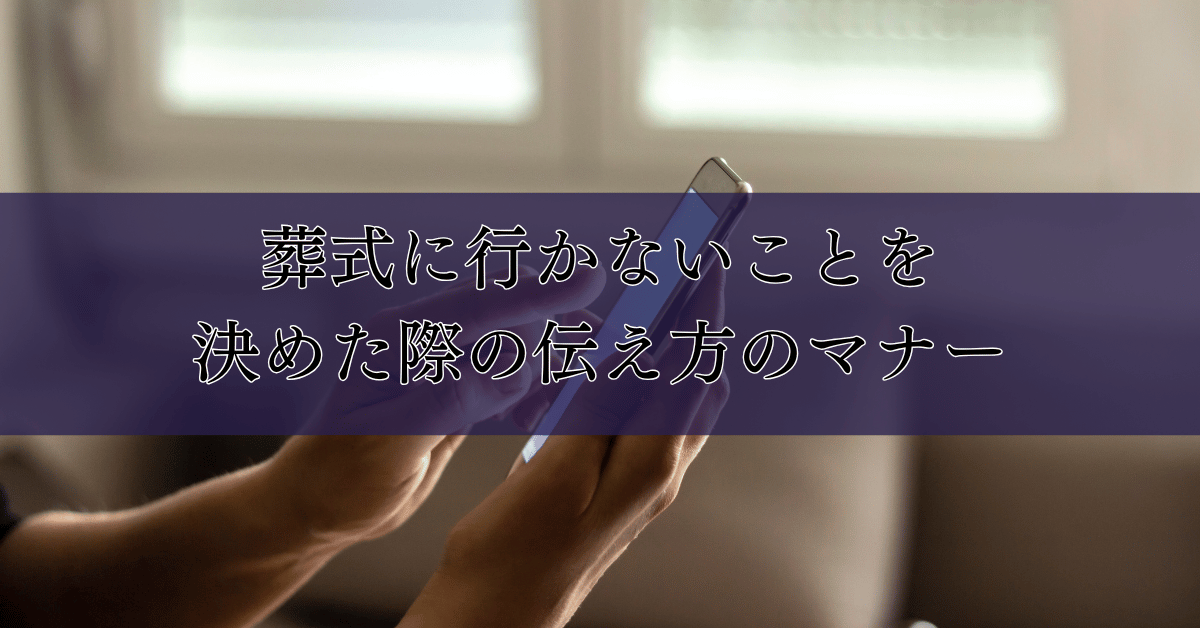
葬式に参列できない場合、遺族にその旨を伝えることは必要不可欠です。
欠席の連絡を丁寧に行うことで、ご遺族に対して失礼のない対応を心がけることができます。
ここでは、葬式に行かないと決めた際に配慮すべきマナーについて解説します。
葬儀は急に行われることが多いため、遺族は参列者の人数をある程度想定して準備を進めています。
そのため、欠席の連絡は早めに入れることがマナーです。
できれば葬儀の日程が決まったらすぐに、遅くとも前日までには連絡を入れるようにしましょう。
葬儀当日はご遺族が多忙で、連絡が取りにくくなる可能性があるためです。
欠席理由を伝える際には、詳細に述べる必要はありません。
「やむを得ない事情のため」や「療養中のため」など、簡潔で控えめな表現で十分です。
例えば、遠方に住んでいる場合は「遠路のため伺えません」と伝えると良いでしょう。
理由が病気の場合も「現在療養中のため」と一言伝えるだけで、遺族に理解してもらえることが多いです。
連絡は、できるだけ電話で行いましょう。
電話で伝えることで、遺族が早く状況を把握でき、直接言葉を交わすことで誠意が伝わりやすくなります。
どうしても電話が難しい場合は、メールや手紙でも構いませんが、手紙は届くまでに時間がかかることを考慮しましょう。
欠席理由を伝える際は、言葉遣いに注意しましょう。
「仕事で行けない」「予定がある」と正直に言いすぎると、非常識と捉えられる場合があります。
適切な表現を選んで、遺族に不快な印象を与えないように配慮することが大切です。
欠席の際には、言葉一つで遺族への印象が大きく変わります。
誠意を持って丁寧に連絡することで、葬儀に参加できないことを理解してもらい、非常識な印象を与えないように努めましょう。
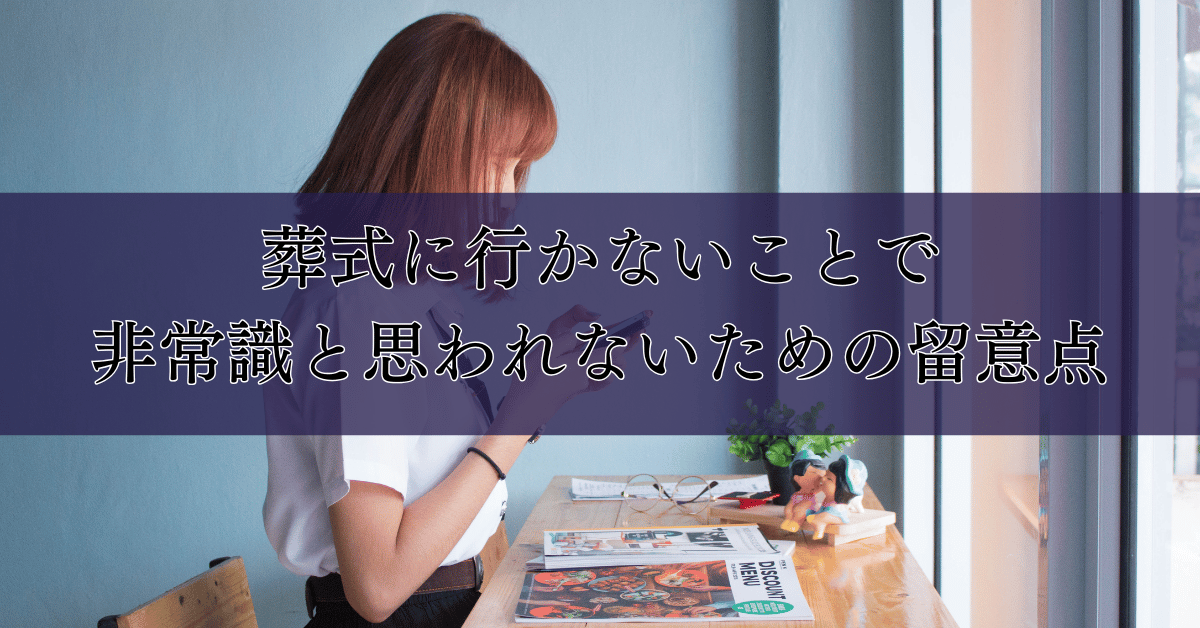
葬式に参列できないことは、さまざまな事情からやむを得ない場合もあります。
しかし、葬式に行かないことで周囲から非常識だと思われないためには、適切な対応とマナーを守ることが重要です。
ここでは、葬式に行かない際に気をつけるべきポイントについて解説します。
葬式に参列できないことが決まったら、できるだけ早めにご遺族や喪主に欠席の旨を伝えましょう。
葬式は遺族にとって大変な時期であり、準備に多くの労力を要します。
早い段階で連絡を入れることで、ご遺族への配慮を示すことができます。
電話が基本ですが、状況によってはメールでも構いません。
欠席する際も、訃報を聞いたらお悔やみの言葉を伝えることは欠かせません。
短いながらも真心を込めて「このたびはお悔やみ申し上げます」や「ご冥福をお祈りいたします」などの言葉を使って伝えましょう。
ただし、宗教や宗派によって適切でない表現もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
葬式に行かない場合は、香典を現金書留で送ることで弔意を示すことができます。
香典に添えて、お悔やみの言葉やご遺族を思いやる一言を記した手紙を同封すると、より誠意が伝わります。
また、弔電を送るのも効果的です。
弔電は、葬儀の前日までに届くよう手配し、故人や遺族への思いを伝える一文を含めるようにしましょう。
葬儀会場に供花や供物を送るのも一つの方法です。
供花は、遺族を慰めるために祭壇を彩る役割がありますが、宗教によって適した花の種類が異なります。
注文時には葬儀の宗教を確認してから手配しましょう。
供花や供物は葬儀場に直接届け、宛名は喪主の名前にすることが一般的です。
通夜や葬儀にどうしても参列できない場合は、後日弔問することでご遺族にお悔やみの気持ちを直接伝えることができます。
弔問の際は、事前にご遺族に連絡し、都合の良い日時を確認しましょう。
香典や供物を持参することで、欠席の際の心遣いを示すことができます。
なお、葬儀後3日から49日の間が弔問に適した期間とされています。
以上のような対応を行うことで、葬式に参列できなかった場合でも非常識と見なされることを防ぎ、ご遺族に対して誠意を伝えることができます。
お電話での無料資料請求・ご相談は
無料
事前資料請求で最大25万円割引
無料
資料請求で喪主のための本プレゼント
お電話での無料資料請求・ご相談は
さがみ典礼の葬儀場を探す
さがみ典礼の葬儀プラン
さがみ典礼のお客様の声
コラム
さがみ典礼のご紹介