
家系図を作って自分のルーツを辿ってみたいと考えたことはありませんか?
家系図を作ることで、自分の先祖がどのような人たちだったのか、その歴史や背景を知ることができます。
ただ、家系図作りに興味はあっても、何から始めたらよいのか、どのように戸籍を取得すればよいのか分からない方も多いでしょう。
実際、家系図作成には戸籍謄本を取得し、その内容を正確に理解してつなげていく必要があります。
この記事では、初心者の方でも分かりやすいよう、家系図作りの最初のステップとなる戸籍謄本の取得方法や先祖を調べる手順について詳しく解説します。
さらに、注意点や手続きのポイントも取り上げているので、これから家系図を作成しようと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

家系図・ご先祖を調べる方法はいくつかありますが、初めての方には具体的な手順を知っておくことが大切です。
自分で行う方法や専門家に依頼する方法を理解し、自分のニーズに合った調査方法を選びましょう。
最も一般的な家系図作成方法は、役所で戸籍謄本を取得し、自分の先祖を追跡していくことです。
戸籍は本籍地の役所で取得する必要があり、これを繰り返すことで家系図が完成します。
現在取得できる戸籍は、明治時代まで遡ることが可能で、家族のルーツを江戸時代後期まで確認できることがあります。
費用は1通あたり数百円程度で、調査範囲によっては数千円~数万円の費用がかかる場合もあります。
戸籍だけでは家系図に不十分な情報がある場合、菩提寺に保管されている過去帳を参考にすることも有効です。
過去帳には、故人の名前、死亡年月日などが記されており、戸籍に記録がない情報を補完できます。
また、図書館の郷土資料や古文書などの文献を調べることで、祖先の職業や当時の生活についても知ることができます。
時間や専門知識に不安がある方は、行政書士や家系図作成の専門業者に依頼するのも一つの方法です。
行政書士は法律や手続きのプロであり、家系図作成のサポートを行っている事務所もあります。
さらに、専門業者は調査範囲が広く、戸籍に加えて現地調査や文献調査を行い、より詳細な家系図を作成することができます。
費用は調査の内容によりますが、簡単な調査で5万円前後から、詳細な調査になると数十万円を超える場合もあります。
家系図作りは、自分のルーツを知るだけでなく、家族のつながりや歴史を感じる大切な作業です。
どの方法を選ぶにせよ、目的や予算に応じて最適な手段を検討してみましょう。
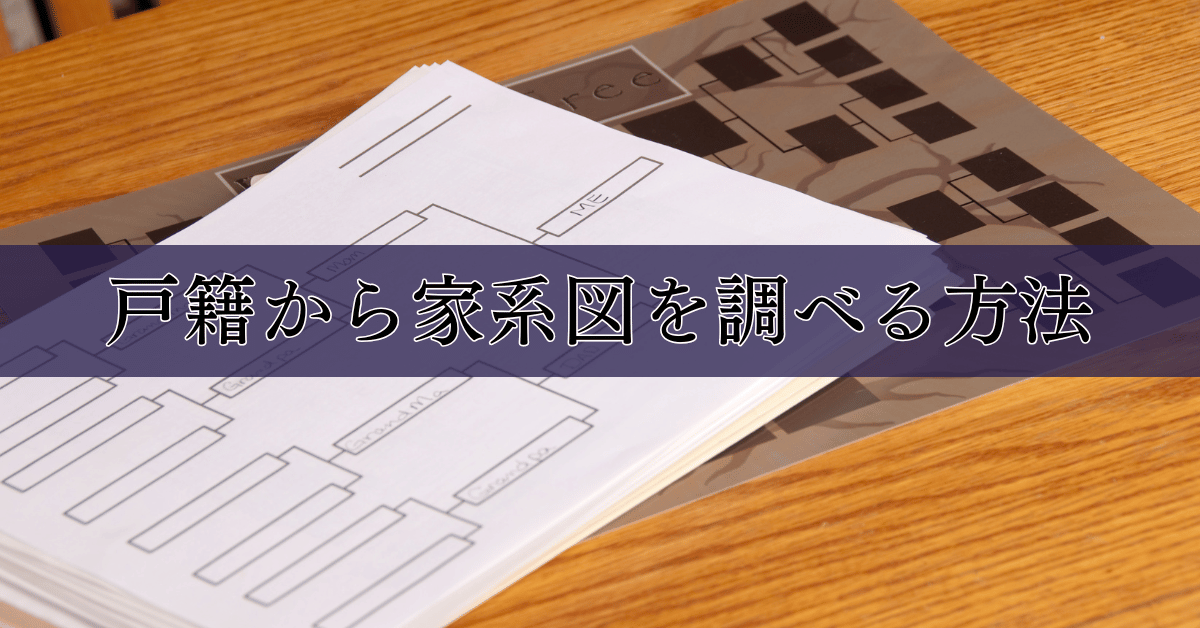
戸籍をもとに家系図を調べることは、自分のルーツを探るための一般的で確実な方法です。
しかし、戸籍の取得や情報の解読には手間がかかるため、事前に手順を把握しておくことが大切です。
ここでは、戸籍を取り寄せて家系図を作成する方法を解説します。
家系図を作成するためには、本籍地のある役所で戸籍謄本を請求します。
請求は窓口で直接行うほか、郵送でも対応可能です。請求できる人は、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)に限られるため注意しましょう。
必要書類
・戸籍交付申請書(自治体ごとに異なる形式で、ウェブサイトからダウンロード可能)
・本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポートなど)
・戸籍取得の手数料(定額小為替など)
・返信用封筒および切手(郵送の場合)
取得した戸籍から情報を読み取り、家系図を作成します。
現在の戸籍だけでなく、過去の除籍謄本や改製原戸籍も収集して情報を集めます。
これにより、家系は江戸時代後期まで遡ることが可能です。ただし、古い戸籍は手書きで記されており、文字のクセや読みにくさがあるため、解読に注意が必要です。
取得した戸籍をもとに、家系図を作成していきます。
祖父母、曾祖父母といった直系の親族を順に辿り、必要であれば複数の役所に戸籍を請求することもあるでしょう。
本籍地が異なる場合や市区町村の合併により本籍が変更された場合は、調査に時間がかかることもあります。
戸籍の保存期間が過ぎている場合、取得できない可能性がある(2023年以降、戸籍の保存期間は150年)。
請求する前に目的と範囲を明確に決めておくことで、無駄を防げます。
古い戸籍の解読には事前知識があるとスムーズです。特に変体仮名や旧字などが含まれるため、解読が難しい場合は専門家のサポートを検討しても良いでしょう。
このように、戸籍を用いた家系図の作成は手間がかかりますが、手順を理解しておくことで効率的に進められます。

戸籍を取り寄せて先祖の情報を収集した後は、そのデータを整理し、見やすい形でまとめる必要があります。
家系図を作成する際に選べる代表的な方法を以下に紹介します。
手書きで家系図をまとめる際には「樹形図」を用いるのが一般的です。
樹形図は、中心となる自分から枝状に親世代、祖父母世代へと繋がっていく形式です。
手書きでは、自分で各世代を整理しやすく、親子関係や兄弟の位置が視覚的に分かりやすくなります。
夫婦を二重線で結ぶ、夫は右・妻は左に配置するなど基本的なルールを守ることで、見やすい家系図を作成できます。
パソコンを使用して家系図を作成する人も増えています。
特にMicrosoft Excelを用いれば、簡単に樹形図を作ることが可能です。
Excel用のテンプレートは、インターネット上で無料でダウンロードできるものもあり、それらを活用すれば入力作業もスムーズです。
デジタル化しておけば、情報の修正や追加が簡単で、手書きよりも効率的に作業が進められます。
最近では、スマートフォンやタブレット用の家系図作成アプリも多く登場しています。
アプリを利用すると、Excelのようにパソコンを起動しなくても、手軽に家系図を作ることができます。
これにより、移動中や空いた時間を活用して情報を入力できるため、スキマ時間を有効に使いたい方には便利です。
アプリは使いやすさや機能が異なるため、目的や作成内容に合ったものを選ぶと良いでしょう。
お電話での無料資料請求・ご相談は
無料
事前資料請求で最大25万円割引
無料
資料請求で喪主のための本プレゼント
お電話での無料資料請求・ご相談は
さがみ典礼の葬儀場を探す
さがみ典礼の葬儀プラン
さがみ典礼のお客様の声
コラム
さがみ典礼のご紹介