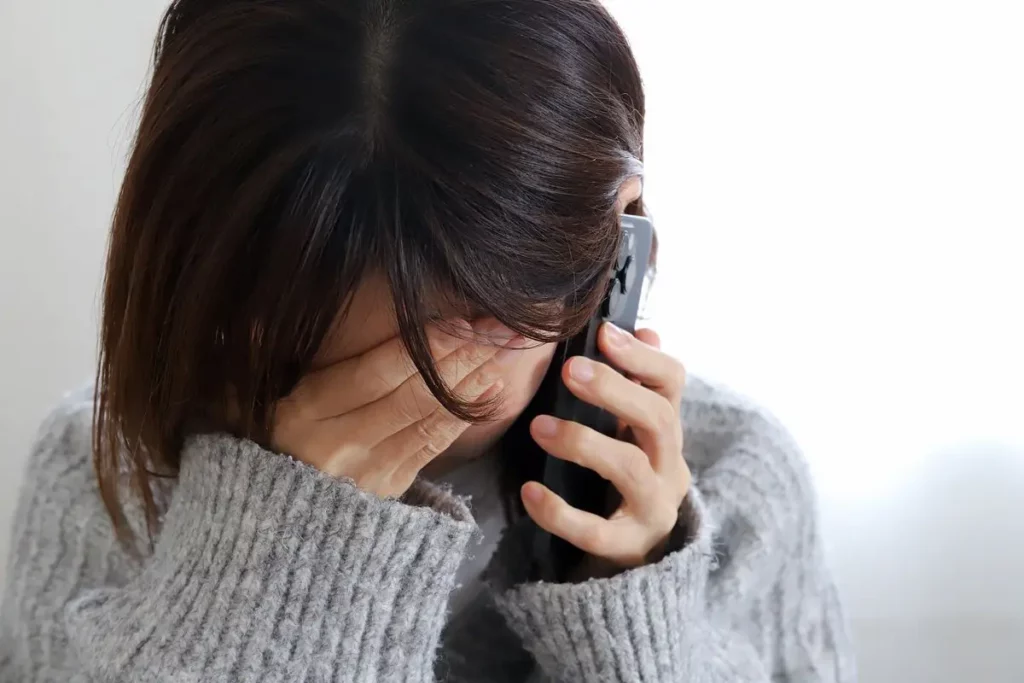
「訃報」は、誰かが亡くなった事実と状況を、ご縁のあった方々に正確に伝えることです。
大切な人を失った直後は気が動転してしまうかもしれませんが、落ち着いて丁寧な対応が求められます。
本記事では、訃報を伝えるべき相手やタイミング、連絡手段、文例など注意すべきマナーをわかりやすく解説します。
不慣れな状況に不安を感じる方も、冷静に対応できるよう、ぜひ本記事をご活用ください。
訃報とは、どなたかが亡くなったことを関係者に伝えることです。「訃」には「人の死を知らせる」、「報」には「事実を伝える」という意味があります。訃報には、逝去の連絡だけでなく、葬儀の日程や会場などの案内も含まれています。
訃報は、電話やメールなどで直接伝えるほか、新聞やインターネット、テレビの報道を通じて広く伝えられることもあります。
訃報を受け取った人は、葬儀に参列したり弔電や香典を送ったりして、故人への追悼の気持ちを表すのが一般的です。
訃報は、どなたかが亡くなった事実を伝える重要な連絡ですが、誰かれかまわず伝えれば良いものではありません。伝える相手や順番、そしてタイミングには十分な配慮が求められます。
葬儀に参列してほしい方や、早めに対応が必要な関係者には、できるだけ速やかに訃報を届けることが大切です。その一方、すぐに知らせる必要のない相手や、葬儀後にあらためて報告する相手もいます。
以下では、訃報を伝える際の一般的な優先順位をご紹介します。あくまで目安であり、故人との関係性やご家族の事情に応じて柔軟に判断して差し支えありません。
訃報の連絡で最も優先すべきは、二親等以内の近親者です。ご遺族や親戚など、葬儀に直接関わる方々には、逝去直後のできるだけ早い段階で知らせなくてはなりません。
特に遠方に住んでいる親族には、移動や宿泊の準備が必要になる場合もあるため、早めの連絡が望まれます。事前に名簿を用意すると、混乱を避けて落ち着いた対応がしやすくなります。
ご遺体の搬送や葬儀の準備を進めるためには、葬儀会社への連絡も早急に行わなければなりません。依頼先が決まっている場合は、まずは葬儀社に連絡を取り、対応を開始してもらいましょう。
すでに菩提寺がある場合は、僧侶などの宗教者にも連絡を入れて、読経や通夜・葬儀の日程調整を行います。なお、宗教者への連絡は、遺族が直接行うこともあれば、葬儀会社が代行してくれる場合もあります。
故人が会社に勤務されていた場合は、所属していた部署の上司や人事担当者へ連絡する必要があります。葬儀の詳細(日程、場所、喪主名など)が確定した後、必要な情報を整理して伝えることで、社内での周知や対応がスムーズに進みます。
また、勤務先から取引先や関係機関へ訃報の連絡をお願いしておくと、遺族側の負担も軽減できるでしょう。
故人と親しかった友人や知人にも、できるだけ早めに訃報を伝えるのが望ましいです。また、町内会や自治会など、地域との関わりがある場合は、担当者や会長などに連絡すると、近隣への周知がスムーズになります。
なお、友人や地域関係者への連絡は、故人との関係性を考慮し、落ち着いてから知らせる場合もあります。
下記は、代表的な訃報の手段です。
訃報にはスピード感が重視されるため、電話で連絡する方法が多用されています。対面で伝えるのが最も丁寧ですが、スピード感を持って各方面に伝えるのには適していません。
また、メール、LINEなどのメッセージアプリで訃報を送るのは、軽々しい、失礼だと捉えられることも考えられます。これらの方法を使うのは、家族や親交の深い親族、普段から気軽にコミュニケーションを取っている方のみに留めておくのが無難です。
連絡する相手との関係性も考慮しながら、必要な情報を伝えましょう。下記は、伝える基本的な情報です。
家族葬を行う場合は、ごく近しい方のみで葬儀を執り行うため、参列いただかない方へは、葬儀日程や会場などの詳細はあえて記載しないのが一般的です。
亡くなられた直後の報告としては、まず1と2の情報、家族葬を執り行うため、香典・供花の儀を辞退する旨を伝えましょう。家族葬の場合は、葬儀が終わってからあらためてお知らせするケースも多いです。
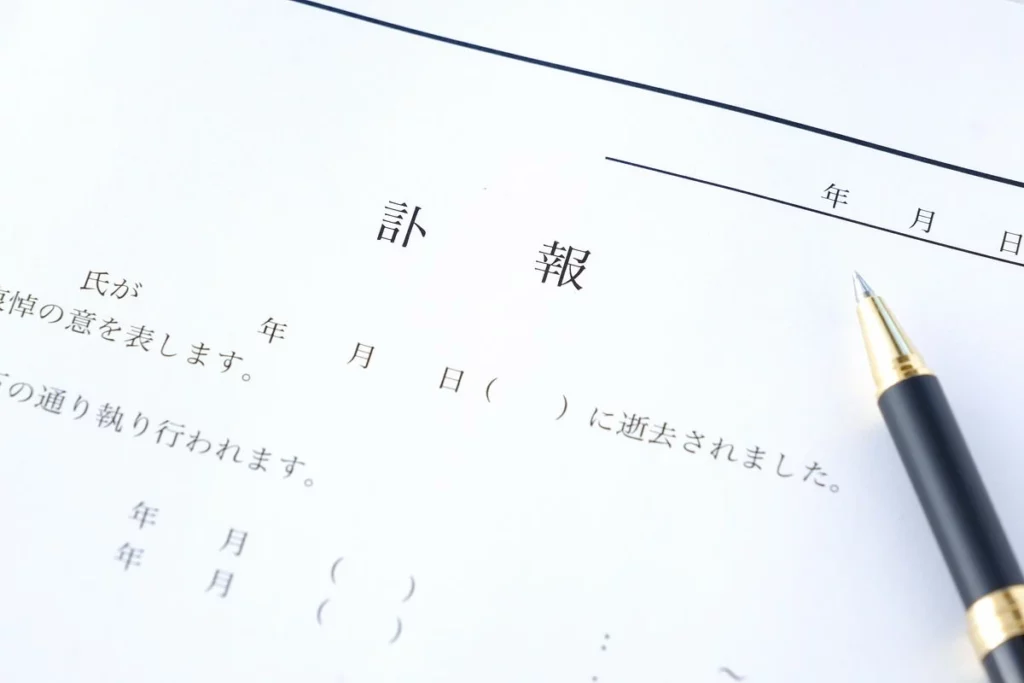
訃報を伝える際によく使われる文例を、電話とメールそれぞれの形式でご紹介します。状況に応じて伝える内容や言葉の表現を調整し、活用してください。
下記に紹介するのは、病院で身内が亡くなられた直後に、近しい親族に電話する際の文例です。
お世話になっております。〇〇〇〇の妻、〇〇〇〇です。
先ほど夫の〇〇〇〇が亡くなりました。
亡くなった場所は、〇〇ホスピタルです。
これから葬儀社に来ていただき、自宅に搬送してもらいます。
葬儀については、その後打ち合わせをすることになると思います。
日程など、決まりましたら、またご連絡いたします。
なにかとお手間をおかけするかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
突然のお電話で失礼いたしました。
混乱しやすい状況の中でも、落ち着いて必要な情報を伝えることが大切です。
下記は、葬儀の日程や会場を伝える場合の文例です。
母〇〇〇〇 儀 かねてより病気療養中のところ、令和〇年〇月〇日に永眠いたしました
生前賜りましたご厚誼に深謝し 謹んでお知らせいたしますなお 通夜式 葬儀告別式は下記の日程で執り行います
通夜式:〇月〇日(〇曜日)〇時より
葬儀告別式:〇月〇日(〇曜日)〇時より〇時まで
場所:〇〇ホール(住所 〇〇市〇〇 〇番地/電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇)
喪主:〇〇〇〇(〇〇)(カッコ内には続柄を記載する)(差出人名)〇〇〇〇
(連絡先)〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
上記の内容を参考に、状況や相手との関係に応じて言葉を調整しご使用ください。
家族葬で身内のみで葬儀を執り行った際に、事後報告として、故人の逝去、葬儀を済ませたこと、生前のお付き合いに感謝する気持ちなどを記した挨拶状を送ることもあります。
喪中はがきの送付で事後報告するケースも珍しくありません。年賀欠礼の文面にて、訃報を記載するケースです。
新聞に掲載される訃報には「死亡記事」と「死亡広告」があります。死亡記事は、新聞社独自の判断で著名人などの死亡や葬儀などの情報を掲載します。
一方、死亡広告は、遺族や法人から新聞社に訃報の掲載を依頼するもので、掲載には料金が発生します。
近年、新聞の購読者数が減少傾向にありますが、地域によっては死亡広告を掲載する慣習が根強く残っています。
訃報を伝える際には、言葉の選び方や文面の形式に十分な配慮が必要です。悲しみの中にある相手に不快な印象を与えないよう、基本的なマナーを守ることが大切です。
訃報を伝える際、特に注意したいポイントは以下の通りです。
それぞれを詳しく解説します。
訃報文では、「、」「。」など文を区切る句読点を使わないのがマナーです。仏事特有の表現で、葬儀が滞りなく進むことを願う意味が込められています。
また、句読点を使用しないのは、毛筆文化では句読点を打たないのが一般的だった歴史的背景も影響しています。現代の訃報では、句読点を使わない代わりに改行やスペースを挟みながら読みやすい文章を作ります。
相手の心情に配慮した温かみのある言葉遣いも忘れないようにしましょう。なお、訃報への返信文でも句読点を使わないのが礼儀とされています。
訃報では、悲しみの中にいる相手に配慮し、「忌み言葉」を避けましょう。
例えば、「たびたび」「また」「重ね重ね」などの重ね言葉は、不幸が繰り返される印象を与えるため、使用を控えます。また、「死ぬ」「急死」など直接的な表現は避け、「逝去」や「永眠」など、やわらかい言い回しにしてください。
さらに、「四(死)」「九(苦)」などの不吉とされる数字や語句にも注意が必要です。宗教や地域によって価値観は異なるため、誰にでも通じる無難な表現を選ぶと安心です。
訃報のお知らせでは、受け取る相手に余計な負担をかけないよう、必要な情報を正確かつ簡潔に伝えることが大切です。
時候の挨拶や冗長な表現は避け、故人の氏名・逝去の日時・通夜や葬儀の日時・会場・喪主など、必要最低限の内容を明瞭にまとめましょう。
故人の人柄や思い出などを伝えたい場合は、訃報とは別のかたちで、あらためてお知らせするのも1つの方法です。
さがみ典礼の「一般葬プラン」は、ご縁のあった多くの方々に見送られ、心穏やかにお別れができる葬儀形式です。
納棺、告別式、火葬を始めとした基本の流れに加え、会葬礼状や生花装飾、祭壇設営、役所・火葬手続きの代行など、必要な準備が一括で整っているため、急なご逝去にも落ち着いて対応できます。
一級葬祭ディレクターの資格を持つ葬儀のプロが一貫してサポートするため、葬儀の進行やマナーに不安がある方でも滞りなく葬儀を執り行えるでしょう。
訃報は、故人の逝去を関係者に正しく伝え、お別れの場を設けるための大切な連絡です。伝える相手や手段、言葉選びには細やかな配慮が求められ、内容は簡潔かつ正確にまとめることが望まれます。
初めて訃報を出す場合や、対応に不安がある時には、葬儀会社のサポートを活用するのも1つの方法です。さがみ典礼の一般葬プランでは、葬儀の準備から訃報文の作成まで経験豊富なスタッフが丁寧に対応してくれます。
大切な人とのお別れを、安心して心を込めて行うためにも、不安な時は専門家の力を借りながら、悔いのないお別れの準備を進めましょう。
お電話での無料資料請求・ご相談は
無料
事前資料請求で最大25万円割引
無料
資料請求で喪主のための本プレゼント
お電話での無料資料請求・ご相談は
さがみ典礼の葬儀場を探す
さがみ典礼の葬儀プラン
さがみ典礼のお客様の声
コラム
さがみ典礼のご紹介