
葬儀に参列した際、小さな袋に入った塩を手渡されたことがあるかもしれません。
この「清め塩」は、体を清めるために使います。
古くから、死は「穢れ(けがれ)」とされ、葬儀後にその穢れを家に持ち帰らないための習慣です。
この記事では、初心者向けに清め塩の使い方とタイミングについて解説します。
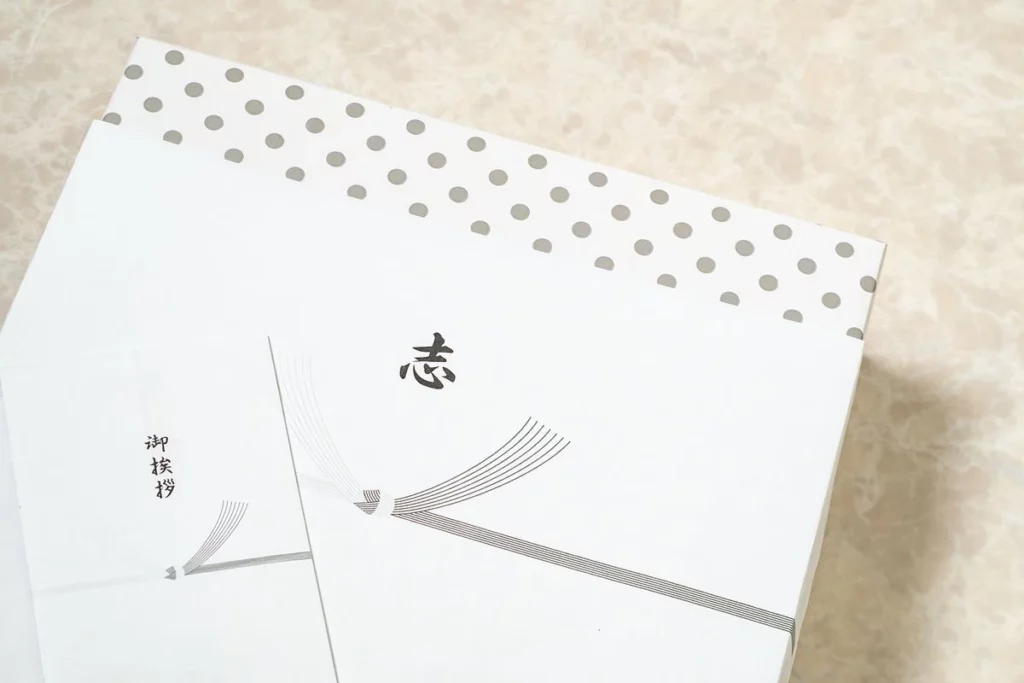
清め塩は、体に付着した穢れ(けがれ)を祓うために使います。
神道では、死は穢れを伴うと考えられ、これを祓うために塩が使われます。
死そのものが穢れではなく、死に伴う邪気を祓うために清め塩を使います。
葬儀から帰宅したら、玄関に入る前に清め塩を使います。
一軒家ならば門の前、集合住宅なら玄関の前で行います。
清め塩は胸、背中、足元の順に振りかけ、体を清めます。
特に背中は他の家族に手伝ってもらうと良いでしょう。
最後に、玄関に入る前に塩を踏むことで、完全に穢れを断ち切ります。
神社での清め塩の使い方も同様です。
神社の境内に入る前に、清め塩を体に振りかけて清めます。
特に神聖な場所に入る前には、より丁寧に行うと良いでしょう。
身内の葬儀後も、同じ手順で清め塩を使います。
特に近親者の場合、穢れが強いとされるため、丁寧に清めることが重要です。
マンションなどの集合住宅では、共有スペースに塩を撒くことが難しい場合があります。
その際は、玄関に入る前に塩を使い、玄関マットや敷地内の目立たない場所で清めるようにしましょう。
もし葬儀後に清め塩を忘れてしまった場合、自宅に戻った後でも塩で体を清めることは可能です。
また、気になる場合は再度神社などで清め塩を使って祓い直すこともできます。
清め塩が余った場合は、適切に処理することが大切です。
自然に還す方法として、庭や植木に撒くか、海水で流すと良いでしょう。
不要な穢れを家に残さないためにも、丁寧に処理することを心がけてください。
清め塩は、一度使ったらその場で処理するのが基本です。
繰り返し使用することは避け、必要に応じて新しい塩を使うようにしましょう。
この記事を参考に、正しい方法で清め塩を使い、穢れを祓う習慣を実践してください。
これにより、自分や家族を守り、平穏な日常を維持することができるでしょう。
お電話での無料資料請求・ご相談は
無料
事前資料請求で最大25万円割引
無料
資料請求で喪主のための本プレゼント
お電話での無料資料請求・ご相談は
さがみ典礼の葬儀場を探す
さがみ典礼の葬儀プラン
さがみ典礼のお客様の声
コラム
さがみ典礼のご紹介