さがみ典礼の葬儀場を探す
さがみ典礼のアフターサポート
さがみ典礼のご紹介
さがみ典礼の葬儀場を探す
さがみ典礼の葬儀プラン
さがみ典礼のお客様の声
コラム
さがみ典礼について
さがみ典礼のアフターサポート
さがみ典礼のご紹介

家族葬は近年注目される新たな葬儀スタイルで、親族や親しい友人のみで少人数で行えることから、多くの方が選択するようになってきました。
しかし、葬儀スタイルだけに具体的な流れや必要な準備物などが分からず、不安を抱える方も少なくありません。
本記事では、家族葬を進める上での一般的な日程・時間や流れ、必要な準備物について詳しく解説します。
また、家族葬の際に気をつけるべきマナーや、必要な準備物についても分かりやすくご紹介します。
これから家族葬を検討される方や、準備に不安を感じている方にとって、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。ぜひ参考にしてください。
家族葬とは、家族や親族、そしてごく親しい友人のみに限り、少人数で行うお葬式です。
一般的な葬儀(一般葬)に比べて参列者の数が少なく、その分、一人ひとりの想いを大切にしながら、故人との時間をゆっくり過ごすことができます。
そのため、家族葬には「親しい方だけで故人を見送りたい」「大きな負担を避けながらも心のこもったお別れをしたい」というご遺族の思いが反映されやすいという特徴がある葬儀形態です。
家族葬を選ぶ際には、参列者の範囲をどこまでにするかが重要なポイントとなります。
家族葬には明確な定義がないため、「誰を呼ぶべきか」という点で迷われる方も多いでしょう。
基本的には家族や親しい友人・知人を中心に行いますが、故人と深い関わりのあった方々には声をかけることが一般的です。
大切なのは、故人に対して敬意を払いながら、ご遺族が後悔のない形で送り出せるようにすることです。
家族葬の流れとしては、通常、通夜と葬儀・告別式の2日間にわたって執り行われますが、現在は1日で執り行っているケースが増えてきています。
この記事では、通夜式・告別式に分けた場合を詳細に解説していきます。

家族葬を執り行う際には、まずご逝去から安置までの流れを正確に理解することが大切です。この段階では遺族が冷静に対応するための準備が求められ、葬儀社との連携をスムーズに進めることが重要です。ご逝去から安置までの手順を把握することで、その後の流れを問題なく進める準備が整います。ここでは、それぞれのステップで確認すべき事項や手続きについて詳しく解説します。
この出来事は、多くの場合予期せぬタイミングで訪れ、心の準備が整っていないまま進行することが一般的です。しかしながら、葬儀を円滑に進めるためには迅速かつ適切な対応が求められます。
病院でのご逝去の場合には、医師により死亡診断書が発行されます。その後、搬送先や葬儀社を決める必要があります。
自宅でのご逝去の場合でも、まず医師を呼び、死亡診断書を取得する必要があります。
この診断書は、火葬や除籍手続きに必要な重要な書類です。
また、看護師によるエンゼルケアが行われ、故人様のお体を整える準備がされます。
もし病院でお亡くなりになった場合、病衣から退院用の服に着替えさせることも必要です。
入院費の支払い方法についても確認しておきましょう。
次に、葬儀社に連絡してご遺体を搬送してもらいます。
病院から自宅や安置施設・葬儀会場への搬送は速やかに行う必要がありますので、事前に葬儀社の連絡先を登録しておくと安心です。専門的な対応が可能な葬儀社に依頼することで、遺族が抱える肉体的、精神的負担を大幅に軽減できます。
例えば、24時間対応の葬儀社に依頼すれば、深夜や早朝にご逝去された場合でも、迅速に対応していただけます。このような葬儀社は、経験豊富なスタッフが適切な手続きを進めてくれるため、遺族の不安を解消し、安心して任せられるでしょう。
お迎えの霊柩車には1~2名まで同乗可能で、可能であれば故人様が生前好きだった場所やもう一度行きたかった場所に立ち寄ることもできます。
安置場所の選定は、ご遺体をどこで安置するかを決める重要なプロセスです。適切に安置することで、ご遺族にとっては心の整理をする大切な時間を確保でき、さらに葬儀の準備も円滑に進められます。この選定にあたっては、衛生面や法律的な配慮が欠かせません。
自宅に安置する場合、ご遺族が故人の近くで共に過ごす時間を持つことができるという利点があります。一方で、斎場や葬儀社の専用施設を利用する選択肢もあります。この施設を利用すれば、専用の設備やスタッフのサポートを受けられるため、手間が軽減されることが大きなメリットです。
安置場所を選ぶ際には、家族の意向や状況を十分に検討することが大切です。例えば、自宅での安置が難しい場合や、ご遺族が短時間で遠方から駆けつけなければならない際には、施設を利用するのが現実的かもしれません。また、宗教儀式や家族の希望により特定の場所が求められることもあります。
これらの判断を下す際には、葬儀の専門家と相談することがすすめられます。葬儀社の担当者がそれぞれの選択肢について丁寧に説明してくれるため、最適な選択をする手助けをしてくれるはずです。慎重な選定を行うことで、故人との重要な時間を大切に過ごし、悔いのない葬儀準備につなげられます。
ご逝去後、速やかに家族や親しい友人への連絡を行うことは非常に重要です。それは故人との最後のお別れに立ち会える機会を提供し、葬儀の準備や段取りをスムーズに進めるためです。特に親しかった方々には速やかに知らせることで、後々の誤解やトラブルを防ぐことができます。
例えば、遠方に住む親族や親しい友人には電話やメッセージを通じて直接連絡を取り、亡くなったこととその詳細を知らせることが求められます。この直接的なコミュニケーションは、遺族が自身の気持ちをしっかりと伝えることにもつながります。その後、葬儀の日程や場所が決まり次第、改めて詳細な情報を伝えることも忘れないようにしましょう。
家族や親しい友人に早めに連絡をし、訃報を共有することで、葬儀や式典がスムーズに進行するだけでなく、精神的な支えとしても大きな役割を果たします。周囲の人々の支援を得ることで、より穏やかに最後のお別れを行うことができることでしょう。

家族葬は少人数で執り行うプライベートな形式の葬儀であり、事前のお打ち合わせが重要です。このセクションでは、喪主の決定から親族や友人への連絡まで、円滑な進行に必要なステップを解説します。
準備段階での打ち合わせでは、まず喪主の役割を明確にし、次に葬儀の日程や場所、内容、費用について家族全員で相談を進めます。このプロセスには全員の意見を取り入れることがスムーズな進行を促します。その後、家族葬にふさわしい小規模な範囲で親族や友人へのご連絡を行うことで最適な規模感を保つことが理想的です。
喪主は葬儀全体の責任者となり、葬儀社や関係者との連絡役を担うなど、重要な役割を果たします。葬儀の準備期間中は、日時や場所の決定をはじめ多くの手続きや調整が必要なため、指揮を執る人がいないと進行が滞る可能性があります。
喪主の具体的な役割には、親族や友人への案内、式次第の確認、宗教者や参列者に対する挨拶などが含まれます。また、葬儀の最中も先頭に立って式を導き、故人への最後のお別れの場面で重要な役割を担うことが多いです。喪主が明確であれば、各手配がスムーズに進み、結果として家族全体の負担を軽減する効果につながります。
一般的には、故人と最も縁の深い人物が喪主を務めることが多いです。例えば、故人の配偶者や長男・長女が喪主を担当するのが一般的なケースですが、家族の事情により兄弟姉妹や他の親族が代行する場合もあります。
高齢の配偶者が喪主となる場合は、名義上は喪主でも実務を別の親族が担当することもあります。
葬儀の日時と場所を決める際には、火葬場の予約状況や参列者の都合を考慮します。
最近では、親族が遠方から駆けつける事情を考慮し、負担を軽減するため、逝去後2~3日以内に家族葬を行うケースが増えています。
また、家族葬の場合、故人との関係が深い人々のみを招くため、場所の選定にも慎重な配慮が必要です。
家族葬の形式や規模によって費用が大きく異なるため、希望や予算に合ったプランを選定する必要があります。適切に相談することで無駄な出費を最小限に抑え、スムーズな準備が進められます。また、このプロセスを通じてプランの内容を具体的に把握し、後々の予期せぬ追加費用を防ぐことができます。
例えば、式場の選択、宗派や宗教的な儀式の有無、花祭壇や供花の選定、参列者への食事の手配、返礼品の数や内容など、細部にわたる具体的な話し合いが必要です。それによって見積もりが明確になり、自分たちの納得いく形での葬儀実施を目指せます。また、プランに含まれるサービス内容を確認することで、必要な項目と不要な項目を精査し、プランニングに反映させることが可能です。
葬儀の進行や式次第についても話し合います。
喪主の挨拶は一般的ですが、故人と特に縁の深い方が挨拶をすることも増えています。
また、式の進行に合わせて、宗教的な儀式やその他の演出についても決定します。
具体的には、通夜式や告別式における挨拶の順番、読経のタイミング、焼香や献花の手順など、進行の細かな項目を決めておくことが大切です。これらを明確にしておくことで、式中の全員が混乱することなく、安心して進行に参加することができます。例えば、喪主や親族がどのタイミングで挨拶を行うべきか、住職や宗教者の儀式がどこに入るのかなどを予め整理しておくだけでも、式はよりスムーズに進行するでしょう。
最後に、葬儀社や担当者と密に連携し、式次第を調整しておくことが大切です。これにより、あらゆる詳細に配慮され、故人を偲ぶ時間に集中できる環境が整います。家族葬を円滑に進めるためには、この事前の準備が欠かせません。
家族葬は通常、招待する方々にだけ案内します。招待する親族や友人には、できるだけ早めに連絡を取りましょう。家族葬とはいえ、遺族の事情や日程の都合を踏まえると、連絡を後回しにするのは避け速やかな連絡をこころがけましょう。
連絡手段としては、通常は電話での連絡が一般的です。電話を通じて故人の逝去、葬儀の日時、場所、服装に関する注意点などを伝えましょう。可能であれば服装の例として「平服で結構です」や「ブラックスーツでご参加ください」など、葬儀の形式に応じた指示を具体的に伝えると親切です。特に遠方から参列する親族や友人には、交通手段や宿泊施設に関するアドバイスを加えることでスムーズな参列が期待できます。また、香典や供花を辞退する場合は、その旨を明確に知らせることが重要です。
家族葬に参列しない方への通知は、丁寧さと配慮を持って行うことが重要です。事前に訃報を伝える際には、家族葬の形式に伴い参列を控える旨を率直かつ思いやりある言葉で説明しましょう。これにより、礼を欠くことなく故人と参列しない方との関係に敬意を示すことができます。
特に、通夜や告別式に参加できないという事実を知らされていないことは、受け取る側にとって悲しく感じられる場合があります。そのため、カードやメール、もしくは電話を用いて適時に伝えることが求められます。文例として、「故人の意向で家族葬を執り行いますため、親族以外の参列はご遠慮いただいております。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。」など、分かりやすく丁寧な案内を心掛けましょう。
この通知によって、参列できない方にも故人への想いや感謝の気持ちを伝えられるだけでなく、円滑な葬儀の進行をサポートする目的にもつながります。また、その際には通知するタイミングや相手の都合を考慮し、適切な手段でお伝えすることを忘れずに行いましょう。配慮を示すことで、大切な人を送り出す場においても、残りの関係性を良好に保つことが可能になります。
また、後日、自宅に弔問に訪れることも考慮し、適切に対応することが望まれます

家族葬では、一般的な葬儀と同様にお通夜を行う場合と行わない場合があり、地域やご遺族の意向によりその形式はさまざまです。
ここでは、通夜式を行うケースを例に説明していきます。
通夜式は故人との最初の別れの場であり、ご遺族や親族が故人を偲ぶ大切な時間です。
以下に、通夜式の一般的な流れと、ご遺族が行うべきことを解説します。
故人を棺桶に納め、旅立ちの準備を整える儀式です。
身なりを整え、愛用していたものなどを棺に納め、故人を心を込めて送り出します。
通夜の3~4時間前に行われるのが一般的です。
受付と着席
通夜式が始まる前に参列者が受付で記帳し、お香典をお渡しします。
その後、指定された席に着席します。席順は、故人の配偶者が祭壇に一番近い席に座り、参列者は血縁の近い方から順に前方から着席していきます。
受付には喪主やご遺族の代表者が立ち、挨拶や対応を行います。
宗教者の入場と開式読経
宗教者が入場し、式が始まります。宗教や宗派によって異なりますが、通常は読経やお祈りが行われます。ご遺族もこの時間に心を落ち着けて故人を偲ぶひとときを過ごします。
焼香や献花
通夜式の中で、参列者が順番に焼香や献花を行います。
これは故人への最後の礼を尽くす儀式であり、ご遺族はその様子を見守ります。
宗教者の指示に従い、丁寧に行うことが大切です。
喪主挨拶
通夜式の最後には、喪主が挨拶を行います。
挨拶では、故人への感謝の言葉や参列者へのお礼を述べます。
喪主はこの挨拶を通して、故人との思い出や家族の気持ちを伝える役割を果たします。
通夜振る舞い
通夜式が終了した後、ご遺族や親しい友人と共に通夜振る舞いを行います。
食事を通じて故人を偲びながら思い出話をすることで、親しい関係を再確認する場となります。
最近では、新型コロナウイルスの影響で、通夜振る舞いを行わず、代わりにお食事カタログギフトを渡すケースも増えています。
参列者の対応
通夜式に参列する方々に対して、丁寧なお礼と対応を心がけます。
特に家族葬では、親しい関係者のみを招待するため、感謝の気持ちを直接伝えることが重要です。
式の進行確認
喪主やご遺族は、葬儀社と協力して式の進行を確認します。予定通りに進行するよう、細かい点まで確認を行います。
お礼の言葉
通夜式の最後に、参列者一人ひとりにお礼を述べるのも良いでしょう。
この場で感謝の気持ちを伝えることが、故人の最後の儀式を締めくくる大切な行為です。

家族葬における告別式は、故人との最後の別れを告げる大切な儀式です。
一般的な葬儀と同様に、家族葬でも式が進行され、火葬へと移ります。
以下は、告別式当日のスケジュールと、ご遺族が行うべきことの詳細です。
ご家族は葬儀場に到着します。到着後、まずは故人とのお別れの準備を確認します。
祭壇の飾りつけや、供花・供物の配置を再確認し、式が滞りなく進行できるように準備を整えます。
また、必要に応じて香典の受け取りや受付の対応方法も確認しておきます。
告別式が開始されます。
僧侶が入場し、読経が行われると共に、参列者が順に焼香を行います。
通常は、喪主が最初に焼香をし、その後にご遺族や近親者が続きます。
家族葬の場合、参列者が限られているため、式全体は比較的短時間で行われます。
式の途中で弔辞や弔電が紹介されることもありますが、家族葬ではこれを省略して終わるケースも増えています。
告別式が終わると、お棺の中にお花を入れ、故人様と最期のお別れを行います。お別れ後、お棺の蓋を閉め「釘打ち」を行い火葬場に向かいます。 葬儀場からお棺をのせた霊柩車が火葬場へ向けて出発する事を「出棺」と言います。
火葬場では「納めの式」が行われ、故人との最後のお別れが行われます。
僧侶による読経の後、参列者が再度焼香を行います。
火葬の際に必要な火葬許可証や骨壺、骨箱を忘れずに持参しましょう。
火葬が始まると約45分から1時間半程度で終了し、遺骨を骨壺に収める「お骨上げ」が行われます。
火葬後、初七日法要が行われることが一般的です。
これは故人が成仏するために行う重要な法要です。
最近では、葬儀当日に初七日法要を併せて行う「繰り上げ初七日法要」が増えています。
法要の後、精進落としとして参列者への食事の席が設けられます。
これは感謝の意を表す場であり、故人を偲びながらの会食となります。
ただし、家族葬では規模が小さいため、精進落としを省略することもあります。
式が全て終了した後は、ご自宅に戻り、故人の遺骨を安置します。
小型の祭壇を設置し、手を合わせる場を設けることが多いです。
葬儀が終わった後には、葬儀社からの最終確認が行われ、費用の精算を行います。
また、今後の手続きや、注意点、法要の準備についても確認しておくと良いでしょう。

家族葬が終わった後も、ご遺族にはいくつかの重要な手続きや対応が必要です。
これらを適切に行うことで、故人を偲ぶ時間を大切にしながらも、後の生活にスムーズに移行できます。
以下に、家族葬後の主な流れを解説します。
葬儀に参加できなかった方々から供花や弔電をいただいた場合、感謝の気持ちを伝えることが大切です。
挨拶状を送り、3,000円〜5,000円程度のお礼の品を添えるのが一般的相場です。
また、葬儀にお招きしなかった方々へは、後日「葬儀は近親者のみで執り行った」と報告する通知を送ります。
年賀状や住所録を活用して連絡することが多く、年末に差し掛かる場合は年賀欠礼の案内と一緒にお知らせすることもあります。
葬儀後には、役所や保険会社への各種手続きを速やかに行う必要があります。
例えば、故人が年金受給者であった場合は、年金の停止手続きを行います。
これは年金不正受給を防ぐためにも重要で、死亡後14日以内に年金受給権者死亡届を提出する必要があります。
また、故人が生命保険に加入していた場合は、保険金請求の手続きを行いましょう。保険会社に連絡し、必要な書類を揃えて提出します。
mp葬儀後の重要な行事として、四十九日の法要があります。
この法要は、故人が成仏するための重要な儀式であり、家族や親族が集まって行われます。
菩提寺がある場合は、僧侶の都合に合わせて日程を決めます。
無宗教の場合は、食事会や小規模な集まりで故人を偲ぶこともあります。
また、法要と合わせて納骨を行うことが多く、お墓に遺骨を納める手続きを進めます。
香典返しは、いただいた香典に対する感謝の気持ちを伝えるために行います。
通常、四十九日法要が終わった後に送る「後返し」が一般的ですが、葬儀当日に即返しするケースもあります。
後返しの場合は、香典の金額に応じた品物を選び、漏れなく発送するよう注意が必要です。
これらの手続きをスムーズに進めることで、葬儀後の煩雑さを減らし、心穏やかに故人を偲ぶことができます。
家族葬はあくまで家族中心の温かい葬儀ですので、その後の対応も丁寧に行いましょう。
家族葬を行う際には、いくつかの重要な準備が必要です。
以下に具体的な準備項目を簡潔にまとめました。
葬儀会社の選定:
家族葬をどの葬儀会社に依頼するかを決めます。信頼できる業者を選ぶことが大切です。
死亡診断書の取得:
病院から死亡診断書をもらい、火葬許可申請などに使用します。
遺体の搬送と安置:
ご遺体を安置する場所を決め、葬儀会社に搬送を依頼します。
寺院への依頼(仏式の場合):
枕経やお葬式の読経をお願いする場合、寺院に依頼を行います。お布施の準備も必要です。
遺影写真の準備:
故人の写真を用意し、遺影として使用するものを選びます。できるだけ笑顔の写真が好ましいです。
参列者の決定と連絡:
家族葬に参加してもらう参列者を決め、連絡をします。実際は家族やごく親しい友人に限ることが多いです。
葬儀内容の打ち合わせ:
葬儀会社と式の流れ、祭壇、棺、供物などについて打ち合わせを行います。参列者の人数に応じて通夜振る舞いや食事の手配も検討します。
家族葬には、特有の注意すべき点やデメリットがいくつかあります。
以下に、家族葬を行う際に気をつけるべきポイントをまとめました。
参列者の範囲を慎重に決める:
家族葬は少人数で行うため、誰を呼ぶかの選び方が重要です。故人を慕う方々が多い場合、呼ばれなかった方から不満を受けることがあります。
参列者を選ぶ際には、故人との関係性や相手の気持ちを考慮し、後悔のないように決定しましょう。
後日の対応を考慮する:
家族葬に参加できなかった友人や知人が、後日弔問に訪れる傾向があります。
そのため、参列できなかった方への対応をあらかじめ考えておくと、後々の負担を減らすことができます。
費用の見積もりに注意:
家族葬は一般葬よりも費用が抑えられることが多いですが、追加費用が発生することもあります。
人数、式場、宗教者へのお礼など、費用に影響する要素を事前に確認し、予算オーバーにならないように注意しましょう。
親族への配慮:
家族葬を選ぶ際には、親族の意見や希望も尊重することが大切です。
親族の中には家族葬に反対する方もいるかもしれません。
トラブルに発展しないように、事前に十分な話し合いを行い、理解を得ることが重要です。
社会的な配慮:
故人の立場や人脈を考慮して、必要な方には訃報を伝えることも重要です。
後から「なぜ知らせてくれなかったのか」といった不満が生じないよう、慎重に判断しましょう。
これらの注意点を把握しておくことで、家族葬を円滑に進め、後悔のないお別れをすることができます。
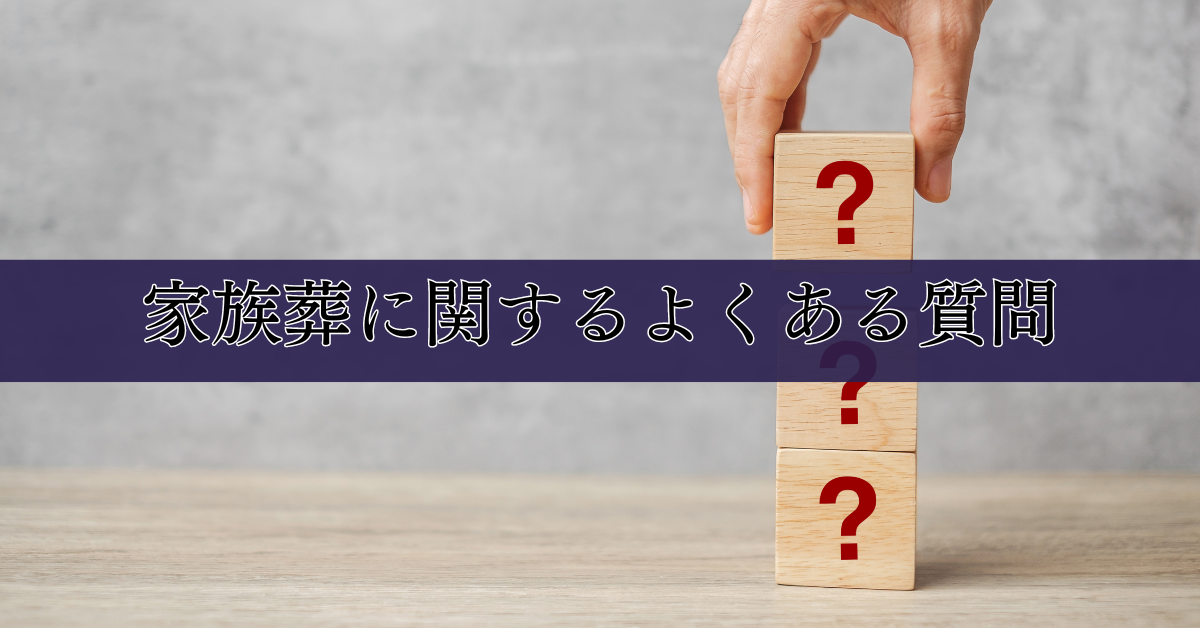
A:
家族葬とは、故人の身内や親しい友人だけを招いて行う小規模な葬儀のことです。
一般的な葬儀とは異なり、参列者の数を限定することで、親しい人々だけが集まり、落ち着いた雰囲気の中で故人を偲ぶことができます。
家族葬は、近年の高齢化や新型コロナウイルスの影響もあり、多くの方が選択する葬儀形式となっています。
具体的には、通夜、告別式、火葬などの儀式は一般葬と同様に行われますが、参列者の人数は通常50名未満とされています。
家族葬を選ぶことで、故人の意思や家族の希望を尊重した、よりプライベートで心温まる葬儀を執り行うことができます。
家族葬と密葬は、いずれも限られた人数で行う葬儀形式ですが、その目的や内容に違いがあります。
家族葬は、故人と親しかった家族や友人のみを招いて行う葬儀です。一般的には50名未満の参列者で、通夜や告別式、火葬といった儀式を執り行います。家族葬は、故人と親しい人々が集まり、穏やかに別れを告げる場として選ばれることが多いです。
密葬は、一般的に「本葬」と呼ばれる大規模な葬儀を前提に、まず身内だけで内々に行う葬儀のことです。密葬の後、一般参列者を招いた本葬やお別れ会を開催します。政治家や芸能人などの著名人が亡くなった場合に多く見られる形式です。また、近年では本葬を行わず、ごく親しい身内だけで葬儀を済ませることを「密葬」と呼ぶケースも増えています。
これらを準備して、故人を心を込めて見送りましょう。
1日家族葬は、告別式と火葬を1日で行います。
葬儀会社への依頼とご安置: 葬儀会社に連絡し、遺体を安置します。
葬儀内容の打ち合わせ: 日程や内容を決めます。
納棺: 遺体を棺に納めます。
告別式: 葬儀会場で告別式を行います。
火葬: 告別式後、火葬を行い、ご遺骨を収骨します。
解散: 精進落としを行い、解散します。
一日葬は短期間で終えられますが、後日の弔問対応も考慮しておきましょう。
家族葬で香典を辞退することは失礼にはなりません。
家族葬は、故人とごく親しい人たちだけで静かにお別れをしたいという目的で行われるため、香典を辞退するのも自然な選択です。
香典辞退の旨を参列者に失礼なく伝えるためには、案内状に「香典はご辞退申し上げます」と明記するか、当日の受付で丁寧に説明するなどの方法があります。
香典を辞退する理由を伝える際は、「故人の遺志である」と説明すると理解を得やすいでしょう。
香典を辞退する場合でも、供花や供物を送る意向がある方もいるため、事前に遺族で対応を決めておきましょう。
無料資料請求で
25万円割引
初めての方もこの一冊で安心 「喪主のための本」 無料プレゼント!

無料資料請求で
25万円割引
初めての方もこの一冊で安心 「喪主のための本」 無料プレゼント!

お電話での無料資料請求・ご相談は
事前資料請求で最大25万円割引