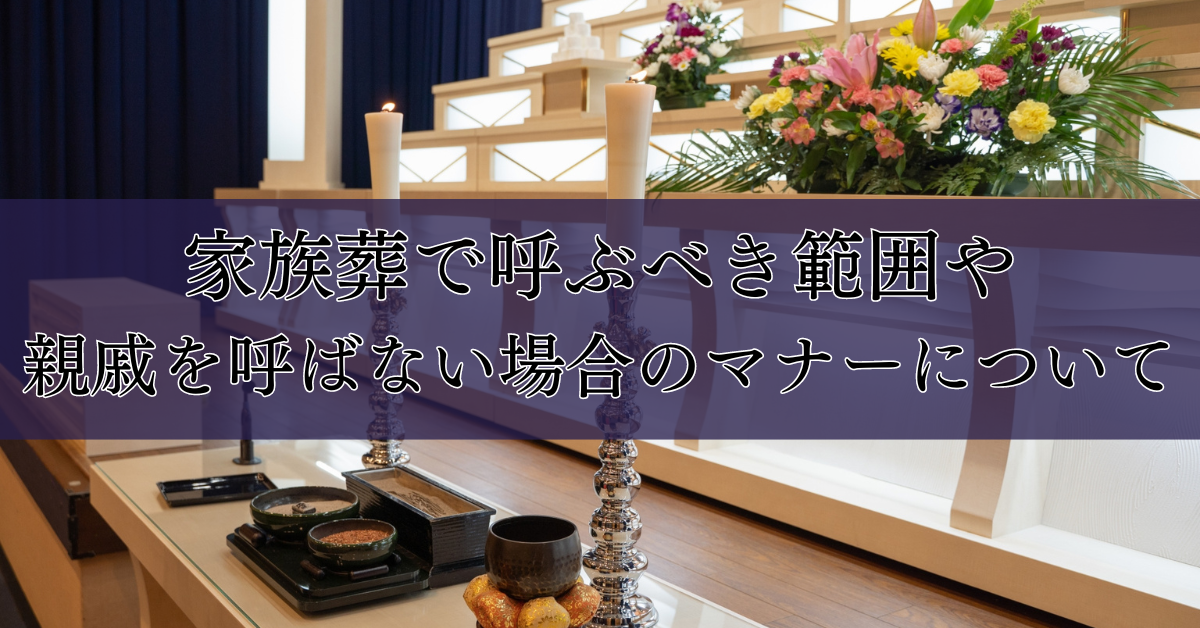
家族葬を行う際、「参列者をどこまで呼ぶか?」という疑問は多くの人が抱える重要な問題です。
家族葬とは、家族や親戚などの近親者のみで故人を見送る小規模な葬儀のことを指します。
しかし、家族葬の定義には明確な線引きがなく、親戚や会社関係者、友人をどこまで呼ぶべきか、また香典の扱いや参列マナーについても迷うことが多いでしょう。
家族葬の参列者範囲とマナーについて初心者にもわかりやすく解説します。
親戚や会社への連絡方法、香典のマナー、そして参列が迷惑にならないようにするためのポイントを詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
家族葬とは?

家族葬とは、家族や親しい親族を中心に、故人と近しい人だけで行う葬儀のことです。
規模や参列人数に明確な決まりはありませんが、一般的には30名以下の小規模な形式が多く見られます。
このため、弔問客の対応に追われることなく、静かに故人を偲ぶことができるのが特徴です。
近年では、新型コロナウイルスの影響や参列者の高齢化などの理由から、家族葬を選ぶ人が増えています。
家族葬は、親しい人だけで行うため、故人をゆっくりと見送れるのが特徴です。
葬儀の流れは一般的な葬儀とほぼ同じですが、規模が小さいため、一人ひとりの想いが反映されやすく、温かみのある雰囲気で故人を偲ぶことができます。
具体的な流れとしては、以下のようになります。
1.ご逝去
2.ご安置
3.家族葬の打ち合わせ
4.お通夜の準備
5.お通夜
6.葬儀・告別式
【関連リンク】
・家族葬とは?初めての方のための内容の解説とアドバイス
家族葬の参列者範囲

参列者をどこまで呼ぶのが一般的か?
家族葬の参列者範囲には明確な定義がありませんが、一般的には2親等以内の親族が参列します。
2親等以内には、配偶者、子、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹が含まれます。
ただし、家族葬という名前からご家族・親族のみが参列できると考えがちですが、故人と親しい友人に参列してもらうことも問題ありません。
参列者の範囲は、家族の意向や故人の遺志を尊重して決定することが重要です。
故人・家族のを意向を尊重
家族葬は、家族の意向を最優先にすることが重要です。
故人の遺志や家族の希望に基づいて、親族や親しい友人を呼ぶかどうかを決定します。
例えば、一緒に暮らしていた家族だけで、親族にも声をかけずに静かに故人を送る場合もあれば、生前親しくしていた友人を呼んで大規模な家族葬を行う場合もあります。
家族葬の柔軟性
家族葬は、一般的な葬儀に比べて小規模なものと思われがちですが、実際には葬儀の大きさや参列者の人数に制限はありません。
家族の考え方や故人の遺志に応じて、どこまで呼ぶかを自由に決められるのが家族葬の魅力です。
また、公正取引委員会が暫定的に定めた定義によれば、「親族や親しい友人など親しい関係者のみが出席して執り行う葬儀」や「参列者50名未満の葬儀」を家族葬としています。
参考:公正取引委員会「葬儀の取引に関する実態報告書」
家族葬を選ぶ理由
あまり「家族」という言葉にこだわらず、ご近所や会社関係の方にはご遠慮いただき、ごく近しい親族を中心に、生前親しくしていた友人をお呼びすることで、家族が弔問客への対応に追われることなく、故人との最後の時間を大切にできるのが家族葬のメリットです。
こうした理由から、多くの人に家族葬が選ばれています。
家族葬の参列者を選ぶ判断基準と連絡のマナー

家族葬を行う際、参列者をどこまで呼ぶかを決めるのは重要なポイントです。
家族や親しい人々が集まり、故人を静かに見送るために、参列者の範囲を明確にすることが大切です。
ここでは、家族葬の参列者を選ぶ判断基準と連絡のマナーについて解説します。
訃報連絡について
訃報を知らせる際には、「訃報」だけを伝えるのか、「葬儀の案内」をするのかを明確にすることが重要です。
訃報のみを伝える場合と、参列をお願いする場合で、連絡内容が異なります。
葬儀の案内をする場合は、日時や場所、服装などの詳細も伝えますが、訃報だけの場合はそれを明確にすることで混乱を避けられます。
参列をお願いする範囲
親族やご友人への連絡マナー:
親族や親しい友人への連絡は、電話や直接の連絡が基本です。
相手の都合を考慮し、早めに連絡を行うことが望ましいです。
特に親しい関係であれば、直接会って伝えるのが丁寧です。
会社関係者への連絡マナー:
会社関係者への連絡は、上司や同僚に対して適切なマナーを守ることが重要です。
メールや社内連絡を利用して、正式に案内を行います。
会社全体への連絡が必要な場合は、社内メールや掲示板などを活用します。
呼ばない方への配慮
家族葬に呼ばない方には、事前にお知らせや挨拶状を送ることで配慮します。
お呼びしない理由を明確に伝えることで、相手の理解を得やすくなります。
「故人の意志により、家族葬を行うことになりました。参列はご遠慮いただけますようお願い申し上げます」
といった文言を使うと良いでしょう。
トラブルを防ぐためのポイント
家族葬を行う際に、参列者をどこまで呼ぶか決めないままにすると、「どうして呼んでくれなかったのか」といったトラブルが発生することがあります。
以下のポイントを押さえておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。
訃報か案内かを明確にする
訃報を葬儀の案内と勘違いして、呼んでいない方が参列することを防ぐために、訃報か葬儀の案内かを明確に伝えましょう。
家族葬で行う場合は、その旨も記載します。
連絡しない時には明確な判断基準を持つ
何らかの理由で家族葬にお呼びしない場合は、明確な判断基準を持つことが重要です。
どのような基準で出席者を選定したかをはっきり説明できるようにしましょう。
呼ぶか迷った場合は呼ぶのが無難
連絡すべきかどうか迷った場合は、呼ぶことをお勧めします。
後になって「どうして自分だけ呼ばれなかったのか」と言われる可能性を避けるためです。
家族葬を選ぶ際の心がけ
家族葬は、故人との最後の時間を大切にするための葬儀形式です。
参列者の範囲を決める際には、家族の意向や故人の遺志を最優先に考え、適切な判断をすることが重要です。
適切な連絡と配慮を行うことで、家族葬が円滑に進行し、故人を心から偲ぶことができるでしょう。
喪主のための本 無料進呈中!
この本には、まさに「必要な時に知っておくべき」情報が満載です。
・病院からの急な危篤の連絡にどう対応すべきか
・愛する人を失った時に何をすべきか
・葬儀での適切な挨拶の仕方 など
喪主を初めて務める方にも分かりやすく、具体的なアドバイスが掲載されています。
この一冊があれば、予期せぬ状況でも冷静かつ適切に行動するための助けになるかと思います。
あなたの大切な時の準備として、ぜひこの貴重な情報源をお手元に置いてください。
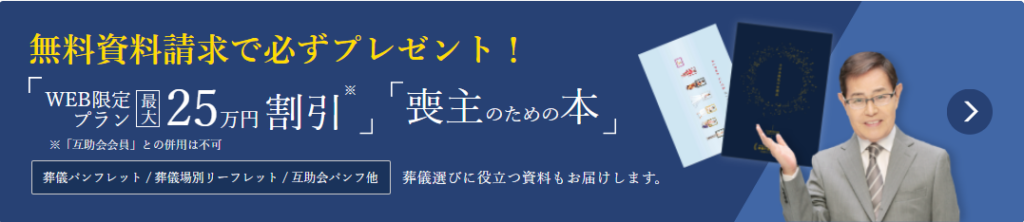

アルファクラブ武蔵野株式会社
葬祭部 さがみ典礼 執行役員
大学卒業後、アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部さがみ典礼に就職してから約20年を葬儀場の現場でお客様の悲しみに寄り添ってきました。
現在は、さがみ典礼の責任者として、現場スタッフとともに残されたご家族のみなさまがより安心して葬儀を進めていただけるお手伝いできることを心掛けています。
2004年3月 東邦大学理学部卒業
2004年4月 アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部 入社
2020年1月 アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部 川口支社 支社長
2021年5月 アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部 副本部長
2022年5月 アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部 本部長
2023年9月 (有)中央福祉葬祭 取締役(アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部 本部長兼務)
2024年5月 アルファクラブ武蔵野(株)葬祭部 執行役員





